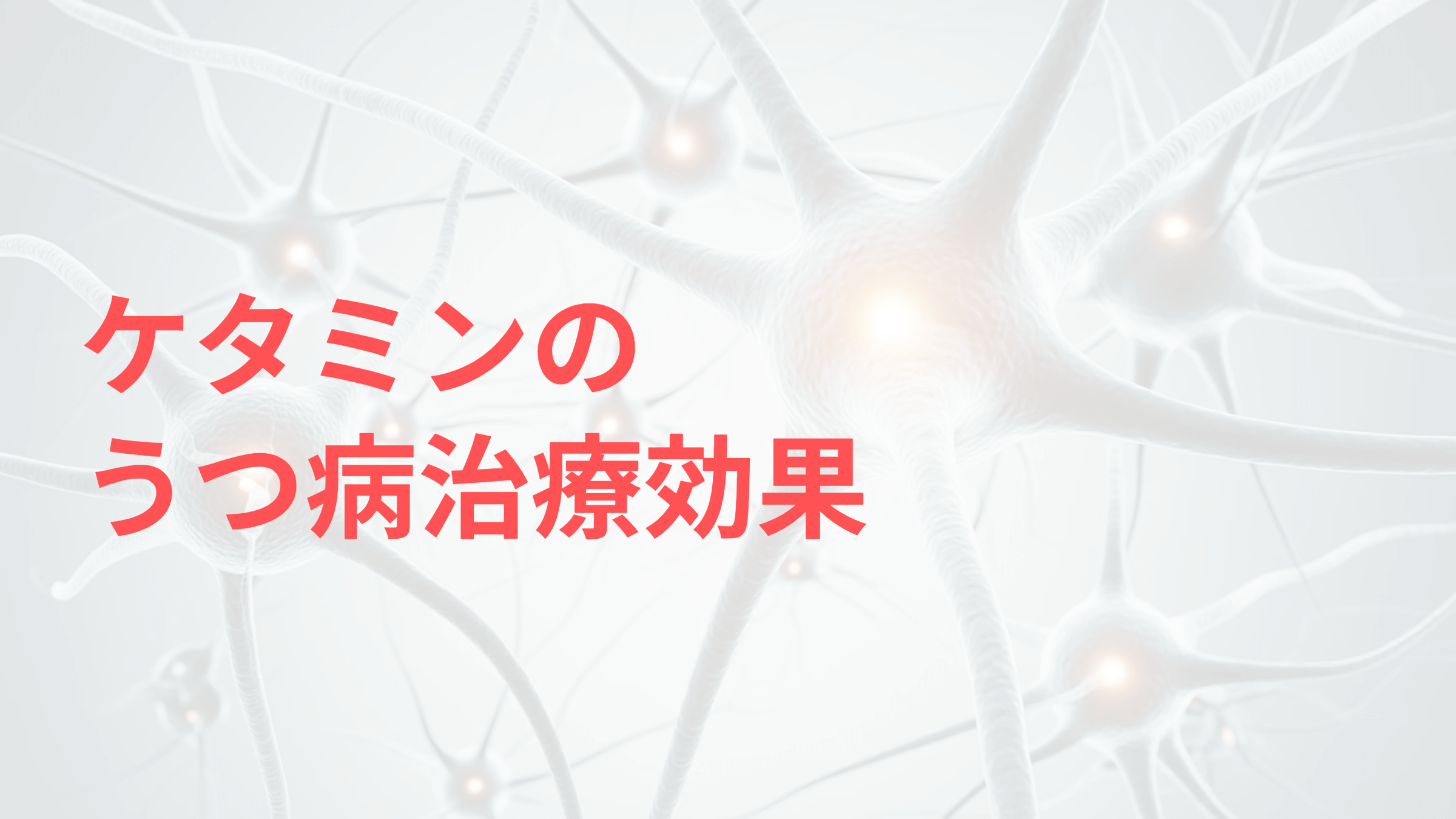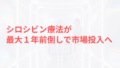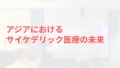従来の抗うつ薬が効果を発揮するまで数週間かかるのに対し、ケタミンは投与後わずか数時間で症状を改善する画期的な治療法として注目されています。本記事では、麻酔薬から抗うつ薬へと進化したケタミンの作用メカニズム、治療効果、そして最新の臨床研究について詳しく紹介します。
ケタミンは数時間でうつ症状を改善する即効性抗うつ薬

ケタミンは、うつ病治療における25年ぶりのブレークスルーとして医学界に革命をもたらしました。2000年に実施された初めての臨床試験で、ケタミンが投与後240分という驚異的な速さでうつ症状を軽減し、その効果が最大72時間持続することが確認されたのです。この発見は、従来の抗うつ薬が効果を示すまでに数週間を要することと比較して、うつ病治療のパラダイムシフトを引き起こしました。
従来の抗うつ薬との決定的な違い
一般的な抗うつ薬であるSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)は、脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の濃度を徐々に調整することで効果を発揮します。そのため、患者が症状の改善を実感するまでに4週間から8週間程度かかることが一般的です。
これに対してケタミンは、グルタミン酸という別の神経伝達物質のシステムに作用するため、即座に脳の神経回路を変化させることができます。特に治療抵抗性うつ病(TRD)、つまり複数の抗うつ薬を試しても改善が見られない患者において、ケタミンの単回投与による奏効率は50%から71%に達することが報告されています。
麻酔薬から抗うつ薬への意外な発見
ケタミンは元々1960年代に解離性麻酔薬として開発され、ベトナム戦争中に広く使用されていました。その安全性プロファイルの良さから手術や緊急医療の現場で重宝されてきた薬剤です。しかし、うつ病への効果が発見されたのは、グルタミン酸系の神経伝達がうつ病の病態生理に関与しているという仮説を検証する過程での偶然の産物でした。
研究者たちは当初、NMDA受容体(N-メチル-D-アスパラギン酸受容体)という脳内の受容体が、うつ病の発症に関わっているのではないかと考えていました。ケタミンはこのNMDA受容体を遮断する作用を持つため、その仮説を検証する目的で臨床試験が行われたのです。結果は研究チームの予想を遥かに超えるものでした。
ケタミンが脳に作用する3つのメカニズム

ケタミンの抗うつ効果を理解するには、その複雑な作用メカニズムを知る必要があります。現在の研究から、ケタミンは少なくとも3つの主要な経路を通じて脳に働きかけることが明らかになっています。
NMDA受容体の阻害作用
ケタミンの最も基本的な作用は、NMDA受容体の非競合的拮抗薬として機能することです。NMDA受容体は脳内でグルタミン酸という興奮性神経伝達物質の信号を受け取る窓口のような役割を果たしています。ケタミンはこの受容体のイオン透過孔の内部をブロックすることで、過剰なグルタミン酸の信号を抑制します。
具体的には、ケタミンがシナプス外のNMDA受容体を選択的にブロックすることで、mTORC1(哺乳類ラパマイシン標的タンパク質複合体1)というタンパク質合成を調節する重要な分子の活性が高まります。このプロセスにより、BDNF(脳由来神経栄養因子)という神経細胞の成長と維持に不可欠なタンパク質の産生が促進されるのです。
もう一つの仮説として「脱抑制理論」があります。これは、ケタミンがGABA作動性抑制性介在ニューロンに発現するNMDA受容体を選択的にブロックすることで、錐体ニューロンの抑制が解除され、グルタミン酸の放出が増加するというものです。放出されたグルタミン酸がAMPA受容体を活性化し、最終的に樹状突起のスパインを増やし、シナプスの可塑性を高めます。
脳の報酬回路の活性化
ケタミンの特筆すべき効果の一つが、外側手綱核(LHb)という脳領域への作用です。外側手綱核は「脳の抗報酬システム」とも呼ばれ、ネガティブな感情や罰の情報処理において中心的な役割を果たしています。うつ病患者では、この外側手綱核の活動が過剰になっていることが知られています。
外側手綱核は、報酬に関わるドーパミン神経やセロトニン神経に対して抑制的に働くため、その活動が高まると報酬系の機能が低下してしまいます。ケタミンは外側手綱核のNMDA受容体依存性のバースト活動(神経細胞が連続して発火する現象)を抑制することで、報酬系への抑制を解除します。この効果はマウスでは最大24時間持続することが確認されており、ケタミンの持続的な抗うつ効果を説明する重要なメカニズムと考えられています。
さらに、ケタミンは前頭前皮質と線条体を含む前頭線条体回路の機能的結合性を高めることも示されています。この回路は報酬処理、動機づけ、快感の経験において中心的な役割を果たしており、うつ病患者ではこの回路の連結性が乱れていることが一貫して報告されています。
神経可塑性の促進
慢性的なストレスは、前頭前皮質や海馬といった脳領域において、シナプスの数の減少、ニューロンの萎縮、さらには神経細胞やグリア細胞の喪失を引き起こします。うつ病はこうした脳の構造的変化と深く関連していると考えられています。
ケタミンは、シナプスの可塑性を回復させ、慢性ストレスによる萎縮を逆転させる作用を持つことが動物モデルで実証されています。シナプスの可塑性とは、脳が情報を処理・保存し、刺激に適応し、短期記憶と長期記憶を形成する基本的な能力のことです。ケタミンはmTORC1の活性化を通じてタンパク質合成を促進し、樹状突起のスパインを増やすことで、失われた神経回路を再構築します。
興味深いことに、ケタミンは投与直後には一時的に認知機能や知覚を混乱させることがありますが、長期的には認知機能を改善する可能性があることも示唆されています。これはAMPA受容体の促進、mTORシグナル伝達、そしてシナプス可塑性に関わるメカニズムを通じて実現されると考えられています。
ケタミンが改善する特徴的な症状

ケタミンは一般的なうつ症状だけでなく、従来の抗うつ薬では治療が困難とされてきた特定の症状に対しても顕著な効果を示すことが明らかになっています。
アンヘドニア(無快感症)への特異的効果
アンヘドニアは、以前は楽しめていた活動から喜びを感じられなくなる状態で、うつ病の中核症状の一つです。この症状は従来の抗うつ薬では改善が難しく、治療後も残存症状として患者の生活の質を大きく損ない、再発リスクを高める要因となっています。現在、アンヘドニアに対してFDAが承認した治療法は存在しません。
ケタミンは、このアンヘドニアに対して特異的な効果を持つことが複数の研究で示されています。治療抵抗性うつ病患者を対象とした探索的研究では、ケタミンが全体的な気分の改善とは独立して、迅速かつ特異的に抗アンヘドニア効果を発揮することが確認されました。これらの効果は、背側前帯状皮質、被殻、海馬、眼窩前頭皮質といった報酬関連脳領域における代謝変化と関連していました。
健常者と治療抵抗性うつ病患者を比較した研究では、ケタミンがうつ病に関連する脳の結合性パターンを正常化することが示されています。特に、背側線条体と腹側線条体、そして前頭前皮質との間の機能的結合性を強化する効果が見られ、これらの結合性の変化はアンヘドニアの軽減と強く相関していました。
ネガティブな記憶の書き換え
ケタミンのもう一つの独特な作用は、既に形成されたネガティブな感情記憶に対する影響です。げっ歯類を用いた感情バイアスモデルでは、動物がストレス状態で学習した刺激を通常避ける傾向がありますが、ケタミンを記憶の想起前に投与すると、このネガティブバイアスが軽減されることが示されました。
重要なのは、ケタミンは学習段階で投与しても効果がなく、想起段階で投与した場合にのみ効果を発揮するという点です。これは従来の抗うつ薬であるベンラファキシンとは対照的です。ベンラファキシンは新しい情報の処理段階で作用しますが、既に符号化された記憶には影響を与えません。この違いが、ケタミンの即効性と従来の抗うつ薬の遅効性を説明する鍵となっている可能性があります。
最近の研究では、ケタミンが内側前頭前皮質の回路を急速に調節してネガティブバイアスを軽減し、その後、報酬関連の手がかりによって再活性化された記憶がポジティブな価値で再符号化されるという2段階の神経心理学的モデルが提唱されています。この再符号化プロセスは内側前頭前皮質におけるタンパク質合成に依存しており、記憶の再固定化という過程と一致しています。
人間を対象とした研究でも興味深い知見が得られています。大量飲酒者を対象とした試験では、アルコール関連の不適応記憶を想起させた後にケタミンを投与すると、飲酒行動が減少し、飲酒日数、アルコール消費量、長期的な飲酒レベルが低下することが示されました。これは、ケタミンが人間においても不適応記憶を破壊できる可能性を示唆しています。
ケタミン療法の現状と安全性の課題

ケタミンの臨床応用は大きく進展していますが、同時にいくつかの重要な課題も浮かび上がっています。
エスケタミン点鼻薬のFDA承認
ケタミンの初期の成功を受けて、エスケタミン(商品名:Spravato)という点鼻薬製剤が開発されました。エスケタミンはケタミンの光学異性体の一つであるS体で、2019年にアメリカ食品医薬品局(FDA)とヨーロッパ医薬品庁(EMA)から承認を取得しました。これは60年ぶりに新しい作用機序を持つ抗うつ薬が承認されたという点で、画期的な出来事でした。
承認に至った主要な臨床試験には、TRANSFORM-2試験(223名)、TRANSFORM-3試験(138名の高齢者対象)、SUSTAIN-1試験(705名)、SUSTAIN-2試験(802名、最長1年間)などがあります。これらの試験では、エスケタミンが既存の抗うつ薬との併用で、治療抵抗性うつ病患者のうつ症状を有意に改善し、寛解に達した患者では再発リスクを51%、安定した反応を示した患者では70%減少させることが示されました。
一般的な副作用には、解離症状、悪心、味覚異常、傾眠、めまいなどがありますが、多くは投与後1.5時間以内に消失する軽度なものでした。長期試験では認知機能が安定して維持されることも確認されています。
しかし、最近のメタアナリシスでは、エスケタミンの効果は抗うつ薬の補助療法として2〜4週間では中程度の効果を示すものの(非定型抗精神病薬による増強療法と同程度)、自殺念慮に対する効果は認められなかったと報告されています。
長期使用の課題と副作用のリスク
ケタミンの安全性について、特に長期使用に関しては未解明の部分が多く残されています。急性期においては、解離症状のため精神病性うつ病への使用は適さず、双極性障害の治療では躁転のリスクに注意が必要とされています。ただし、リチウムやバルプロ酸で安定している双極性I型またはII型うつ病患者15名を対象とした二重盲検クロスオーバー試験では、単回のケタミン投与が40分以内にうつ症状と自殺念慮を有意に軽減し、最長3日間持続したものの、気分の転換は見られませんでした。
長期的には、ケタミンには乱用の可能性があり、膀胱への毒性や脳への影響が人間においてどの程度であるかは不確かです。現時点で最も強固なエビデンスは、エスケタミンの第III相試験から得られており、長期使用は一般的に安全であることが示唆されています。
静脈内ケタミンに関する最大規模の研究は、治療抵抗性うつ病に対するケタミンと電気けいれん療法(ECT)を比較した非劣性試験で、403名の被験者(ケタミン群200名)を対象に6ヶ月間の追跡調査が行われました。この試験では、ケタミンはECTに対して非劣性であり、全体的に安全なプロファイルを示しました。
また、ケタミンが産後うつ病の予防にも有効である可能性を示す研究も報告されています。予定帝王切開時にケタミンを投与することで、出産後の気分障害や不安障害の発症を防ぐ効果が期待されています。産後うつ病は母親の10〜20%に影響を与えるとされており、現在FDA承認を受けている治療薬はブレキサノロンのみです。ケタミン投与が産後うつ病症状の予防に役立つ可能性が示されていますが、帝王切開を受ける女性における有効性と安全性を確認するにはさらなる研究が必要です。
まとめ:ケタミンがもたらすうつ病治療の新時代
ケタミンは、うつ病治療における真のパラダイムシフトを象徴する薬剤です。従来の抗うつ薬が効果を発揮するまでに数週間を要するのに対し、ケタミンは投与後数時間で症状を改善するという即効性を持ち、治療抵抗性うつ病患者に新たな希望をもたらしました。
その作用メカニズムは、NMDA受容体の阻害、外側手綱核の活動抑制、報酬回路の活性化、そして神経可塑性の促進という複数の経路を通じて実現されています。特に、従来の抗うつ薬では治療が困難だったアンヘドニアへの効果や、ネガティブな記憶を書き換える能力は、ケタミンの独特な治療特性を示しています。
エスケタミン点鼻薬のFDA承認により、ケタミン療法は臨床現場で実用化されつつありますが、長期的な安全性プロファイル、乱用リスク、膀胱や脳への潜在的な毒性など、解決すべき課題も残されています。また、解離症状が抗うつ効果に必要なのか、オピオイド系への作用がどの程度関与しているのかといった基礎的な疑問も完全には解明されていません。
それでも、ケタミンの研究から得られた知見は、グルタミン酸系という新しい治療標的の可能性を明らかにし、より安全で効果的な次世代の即効性抗うつ薬の開発への道を切り開いています。産後うつ病の予防やストレス耐性の強化といった予防的応用の可能性も示されており、ケタミンは単なる治療薬を超えた、精神医学の新たな地平を切り開く存在となっているのです。
Costi, S., Wigg, C., Pulcu, E., Murphy, S. E., & Harmer, C. J. (2025). The cognitive neuroscience of ketamine in major depression. Brain : a journal of neurology, 148(10), 3496–3504. https://doi.org/10.1093/brain/awaf242
本記事は情報提供のみを目的としており、医療アドバイスではありません。
精神的・身体的な問題を抱えている方は、必ず医療専門家にご相談ください。
また、日本国内でのサイケデリック物質の所持・使用は法律で禁止されています。